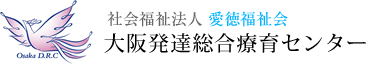愛徳福祉会 法人概要
理念
私たちは障がいを持つ人々が、地域において安心して生活できるよう支援します。
運営方針
- 保健・医療・福祉の緊密なチーム活動をもって生活支援をおこないます。
- 行政機関・医療機関および各種社会資源と連携しその組織化に努めます。
- 広く地域社会に法人の活動に対する理解と参加を呼びかけます。
- 職員は個々の専門性の向上に努めるとともに、法人運営に積極的に参加します。
法人概要
| 施設及び経営主体 | 社会福祉法人 愛徳福祉会 |
|---|---|
| 施設名 | 大阪発達総合療育センター Osaka Developmental Rehabilitation Center |
| 保険医療機関 | 南大阪小児リハビリテーション病院 |
| 住所 | 〒 546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目11番21号 |
| TEL / FAX | 06-6699-8731(代表)/ 06-6699-8134 |
| info@osaka-drc.jp | |
| ウェブサイト | http://osaka-drc.jp |
| 設立年月日 | 昭和57年4月1日 |
| 診療科目 | 整形外科 / 小児科 / 小児外科 / リハビリテーション科 / 歯科 / 泌尿器科 |
| 施設基準 | 厚生労働大臣の定める施設基準等の届出事項 施設基準 |
組織図
法人沿革
| 1970年 |
|
|---|---|
| 1971年 |
|
| 1972年 |
|
| 1973年 |
|
| 1974年 |
|
| 1975年 |
|
| 1977年 |
|
| 1978年 |
|
| 1979年 |
|
| 1980年 |
|
| 1982年 |
|
| 1983年 |
|
| 1984年 |
|
| 1985年 |
|
| 1987年 |
|
| 1989年(平成元年) |
|
| 1990年 |
|
| 1994年 |
|
| 1999年 |
|
| 2000年 |
|
| 2002年 |
|
| 2004年 |
|
| 2006年 |
|
| 2007年 |
重症心身障害児・者施設60床、ショートステイ20床、肢体不自由児施設40床、計120床
|
| 2008年 |
|
| 2009年 |
|
| 2010年 |
|
| 2013年 |
|
| 2015年 |
|
| 2016年 |
|
| 2021年 |
※高木賞とは、わが国で初めて肢体不自由児療育を体系だてられた故高木憲次博士を記念し設けられたもので、顕著な功績、優秀な研究を行った者に授与されるものです。 |
| 2022年 |
|